製造業におけるISOとは?基本から導入までわかりやすく解説
2025.06.10
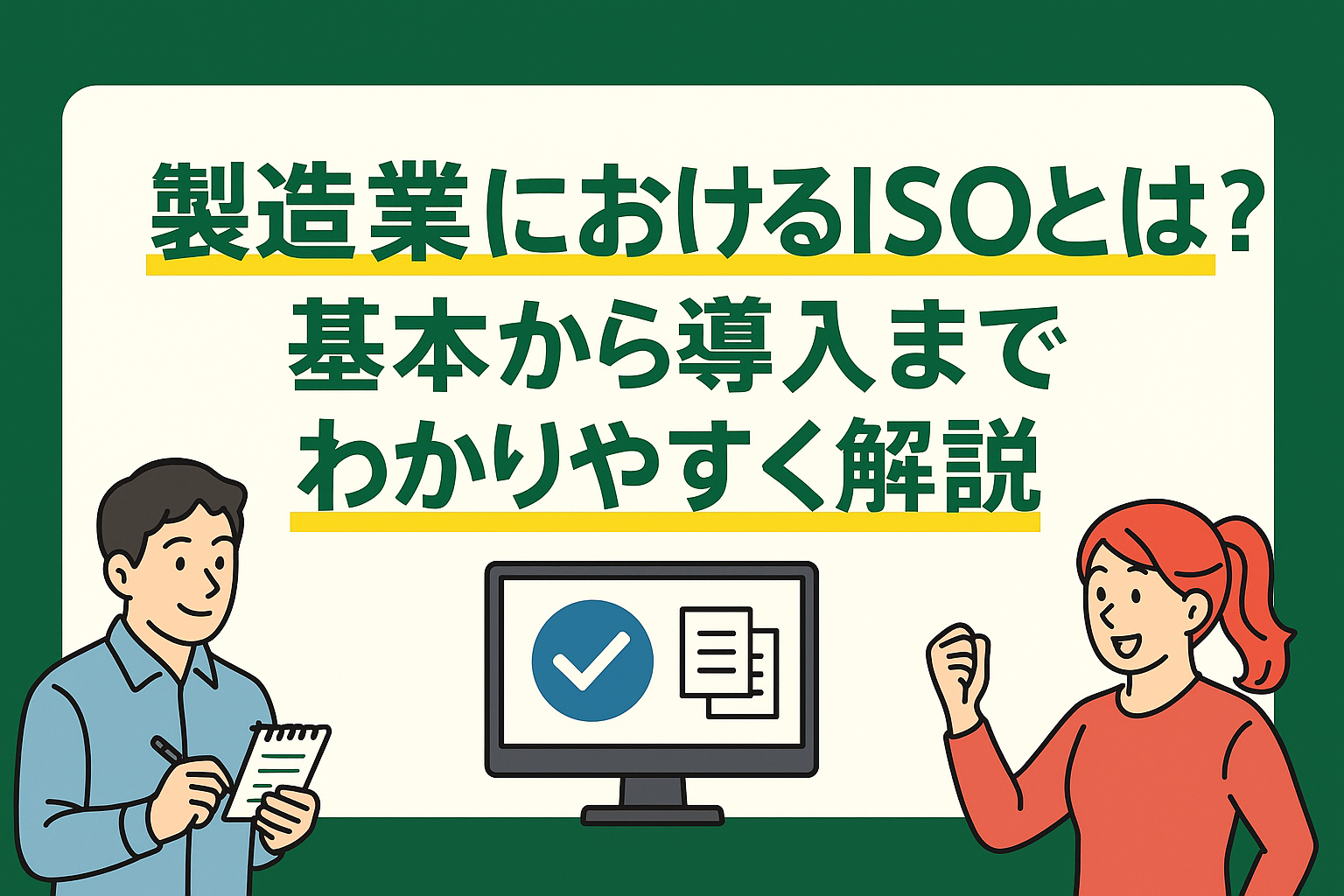
🛠️「ISOって社内でよく聞くけど、実はよく分かっていない…」
🌱「製造業ではなぜISOが重要なの?」
📋「うちの会社もISOを取るらしいけど、どんな準備が必要なんだろう…」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、本記事では「製造業におけるISO」について基本からやさしく解説します。
ISOは、製品やサービスの品質や安全性を確保するための国際的な規格です。
特に製造業では、顧客からの信頼を得るうえでも、社内の体制を整えるうえでも、欠かせない存在となっています。
この記事では、ISOの概要や製造業でよく使われる代表的な規格(ISO9001、ISO14001)、取得のメリット、認証までの流れ、費用の目安までを一通りカバー。ISOの導入をしたい初心者の方や、社内で取得済みのISOについて基本的なことが知りたい設計者におすすめな内容となっています。
目次
ISOとは
ISO(アイエスオー)とは、「International Organization for Standardization(国際標準化機構)」の略称で、世界中の製品やサービス、業務のやり方などに共通の“ものさし”を定めている国際機関です。
このISOが定める国際的な共通規格を「ISO規格」と呼びます。たとえば、「製品の品質をどう管理するべきか」「環境に配慮した業務運営とはどうあるべきか」といった内容が、ISO規格として文書化されています。
企業がこれに沿ったマネジメント体制を整えていることを、第三者機関によって審査・認証されるのが「ISO認証」です。
とくに製造業では、以下のような場面でISOが重要視されます。
✅顧客から「ISO認証を取得していますか?」と聞かれる
✅大手企業のサプライヤーになるための条件に「ISO認証取得」が含まれる
✅社内の品質トラブルやクレームを減らすため、マネジメント体制の見直しを行いたい
このように、ISOとは企業の品質や信頼性を支え、取得することで顧客から選ばれるための”お墨付き”となる側面もあります。
なお、ISOは厳密には国際標準化機構の英語の頭文字からではなく、ギリシャ語の「isos(等しい)」に由来した略称だそうです。これは、上記機構の略称が言語が異なると変わってしまう(英語だと”IOS”、フランス語だと”OIN”)ため、世界的に呼称を統一したい創設者の想いがあったようです。
参考:About ISO
ISO認証取得のメリット
製造業においてISO認証を取得するメリットを3つ紹介します。
①顧客や取引先からの信頼を得られる
製造業は、多くの部品や材料、工程が組み合わさって製品をつくり上げる業種です。そのため、品質のばらつきによるトラブルが発生しやすく、安定した品質管理体制が、企業の評価に直結します。
ISO認証を取得していることで、「この会社は一定の品質を担保できる体制が整っている」と対外的に証明できます。特に大手企業や海外との取引では、ISO取得がビジネスの前提条件になるケースも少なくありません。
②クレームや不良対応のリスクを減らせる
ISO認証の取得には、自社の企業活動にかかわる文書の記録・改善が求められるため、製品不良発生時にも「製造工程で何が起きていたか」を追跡しやすいです。
そのため、トラブルの予防やクレーム発生時の対応スピードの向上にもつながります。
③教育や改善の仕組みが根付く
ISO規格には「継続的改善」や「力量の明確化」といった考え方が含まれており、社員教育やマニュアル整備の習慣化が進みます。
この仕組みにより新人が入ってもスムーズに現場に馴染みやすくなり、ベテラン頼りの属人化リスクを減らす効果も期待できます。
製造業でよく使われるISO規格(ISO9001、ISO14001)
製造業で取得されることが多い代表的なISO規格は、ISO9001(品質マネジメント)とISO14001(環境マネジメント)の2つです。
ISO9001:品質マネジメントシステム(QMS)
ISO9001は、「製品やサービスの品質を安定させ、顧客満足を高めるためのマネジメントシステム」に関する国際規格です。
この規格では、「設計・製造・出荷までの各工程をどう管理し、改善していくか」といった品質管理の枠組みが定められています。
ISO9001のポイントは、ルールを定めてそれを運用し、効果をチェックして改善するというPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの考え方。
「不良品を出さないためにどうすればいいか」「顧客クレームを減らすにはどんな仕組みが必要か」といった視点から、日々の業務を見直すことが求められます。
特に、以下のような企業にとっては導入の意義が大きい規格です:
✅ 製品の品質に関する問い合わせやクレームが増えている
✅ 作業手順が属人化していて、品質が安定しない
✅ 顧客から「品質保証体制を見せてほしい」と言われることがある
ISO14001:環境マネジメントシステム(EMS)
ISO14001は、「企業活動が環境に与える影響を管理・削減するためのマネジメントシステム」に関する国際規格です。
工場や設備を持つ製造業では、エネルギー消費、産業廃棄物の排出、水資源の使用など、環境負荷が大きくなりがちです。
ISO14001では、こうしたリスクを洗い出し、環境への負荷を最小限に抑えるための管理体制の構築が求められます。
たとえば、次のような取り組みが対象となります:
✅ 電力や燃料の使用量を見える化し、効率化を図る
✅ 廃棄物をリサイクルする仕組みを整備する
✅ 環境法令の遵守状況を定期的に確認する
最近では、サステナビリティ(持続可能性)への関心が高まっており、ISO14001を取得している企業は「環境に配慮している会社」としての信頼を得やすくなる傾向があります。
ISO認証を取得する流れ

ISO認証の取得には、いくつかのステップがあります。特別な資格や免許が必要なわけではありませんが、計画的な準備と社内の協力体制が求められます。
ここでは、ISO9001やISO14001の取得に共通する、一般的な流れを5つのステップに分けて紹介します。
ステップ1:現状の把握と方針決定
まずは、自社の業務がISOの要求事項にどれくらい適合しているかを確認し、取得する規格と範囲を決めるところから始めます。
たとえば、「品質管理の強化を目的に、製造部門だけでISO9001を取得する」といった具合に、対象部門や目的を明確にしましょう。
ステップ2:マネジメントシステムの構築
次に、ISOの要求事項を満たすために、ルールや手順書、記録の仕組みなどを社内に整備します。これを「マネジメントシステムの構築」と呼びます。
たとえば、作業手順の明文化、品質記録のフォーマット整備、教育訓練の実施などが必要です。
ISOの取得は準備や審査のためのハードルがあるので、外部のコンサルタントを活用する企業も多いです。外部からのISOに関する知見と現場の運用状況とのすり合わせが成功のカギとなります。
ステップ3:内部監査と見直し
ルールを整えたら、それが実際に現場で運用されているかを確認するために内部監査(社内チェック)を行います。
また、監査結果をもとに経営層が改善の必要点を確認し、「マネジメントレビュー(見直し)」を行います。
ステップ4:外部監査(認証審査)
準備が整ったら、認証機関に依頼して外部審査(ISO審査)を受けます。一般的には以下の2段階で行われます:
第1段階審査(書類審査):マネジメントシステムが整備されているか確認
第2段階審査(実地審査):実際に現場でルールが守られているかを確認
不適合が指摘された場合は、是正処置(改善)を行ったうえで再審査を受けます。
ステップ5:認証取得と運用開始
審査に合格すると、ISO認証書が発行されます。晴れてISO認証を取得しましたが、ある意味ここからがスタートです。取得後も、仕組みを継続的に運用・改善していくことが求められます。
また、ISOには「年1~2回の維持審査」と「3年ごとの更新審査」があり、体制が継続的に機能しているかを定期的にチェックします。
ISOの取得は一朝一夕にはできませんが、手順を踏んで進めれば、特別な企業でなくても十分に対応可能です。まずは社内で「なぜ取得するのか」を共有し、計画的に進めていきましょう。
ISO取得費用の目安
ISO認証の取得には、審査にかかる費用と準備にかかる内部コストの両方が発生します。ここでは、よくある費用の目安と、認証を依頼できる主な機関について紹介します。
ISO認証にかかる費用の目安
ISOの取得費用は、企業の規模や従業員数、認証の範囲、審査を依頼する機関によって変わりますが、中小製造業の場合、一般的には以下のような金額感になります。
| 費用項目 | 内容 | 目安(概算) |
| 審査料(初回) | 書類・現場審査にかかる費用 | 30~100万円程度 |
| 登録料・証書発行費用 | 認証機関による登録・証書発行などの費用 | 3万円~5万円前後 |
| 維持審査料(年1~2回) | 認証維持のための年次審査 | 毎年20~50万円程度 |
| コンサルティング費用 | 必要に応じて。取得にあたり、外部支援を依頼する場合の費用 | 数十万円~数百万円 |
これに加えて、社内での文書作成や教育、打ち合わせなどの人的コストも発生します。初めてISOを取得する場合は、全体で少なくとも100万〜200万円程度を見込んでおくのが一般的です。
ISO認証の審査機関
ISOは、第三者の認証機関に審査を依頼し、合格することで認証が得られます。
日本でよく使われている代表的な審査機関には以下があります:
・JQA(一般財団法人 日本品質保証機構)
・JICQA(日本検査キューエイ株式会社)
・BSIグループジャパン株式会社
・SGSジャパン株式会社
・DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
それぞれに特徴や強みがあり、審査の進め方や費用感も異なります。事前に複数社から見積もりを取ることで、自社に合った審査機関を選ぶことができます。
よくある質問
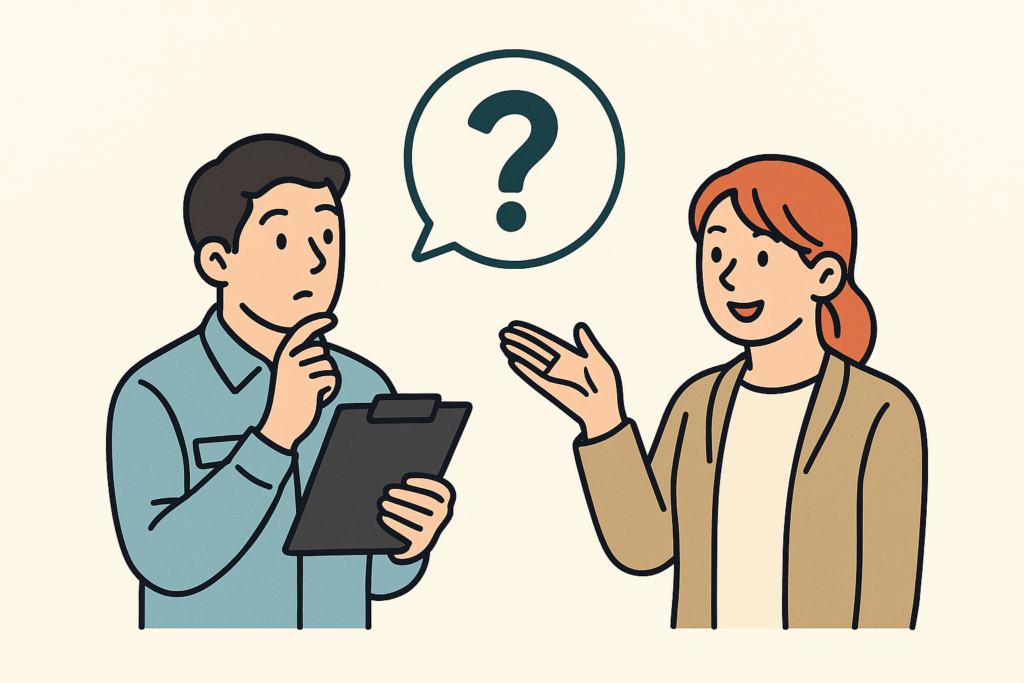
ここでは、ISO認証に関して製造業の現場でよく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。導入を検討している方は、自社に当てはめて参考にしてみてください。
Q1:小規模な会社でもISO認証は取れますか?
はい、取得可能です。
ISOの規格は企業規模を問わず適用できるよう設計されており、数名規模の中小企業でも取得している例は多数あります。
ただし、必要な文書類の整備や運用ルールの明文化が求められるため、体制づくりには一定の労力が必要です。
Q2:社内に専門知識がなくても大丈夫ですか?
問題ありません。
ISO取得にあたっては、社内でゼロから勉強する方法もありますし、外部のコンサルタントや支援機関にサポートを依頼することも可能です。
中小企業向けには、各地域の商工会議所や中小企業支援機関などが無料相談に応じているケースもあります。
Q3:一度取得すれば、それで終わりですか?
いいえ、ISOは一度取れば終わりという制度ではありません。
認証後は毎年1~2回の「維持審査」、3年ごとの「更新審査」があります。これにより、マネジメントシステムが継続的に運用・改善されているかがチェックされます。
Q4:ISOを取得すると、必ず業績が上がるのでしょうか?
ISOはあくまで「体制や仕組みの整備」が目的であり、売り上げ向上を保証するものではありません。
しかし、品質トラブルの減少や顧客満足度の向上、社内の業務改善など、中長期的には業績面にもプラスの影響をもたらすことが期待されます。
Q5:ISO9001とISO14001、どちらから取るべきですか?
一般的には、ISO 9001から取得するほうが良いでしょう。ISO9001は既存の製造プロセスを整えることで着手でき、不良率低減や商談受注率向上など収益効果が早期に現れやすいからです。
ただし、取引先が環境マネジメントの取得を優先的に要求している場合、投資家・金融機関が ESG スコアを重視し、資金調達コストに影響する場合は、14001の先行取得も検討します。


